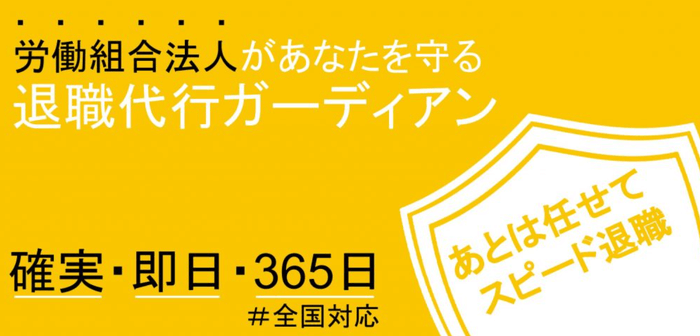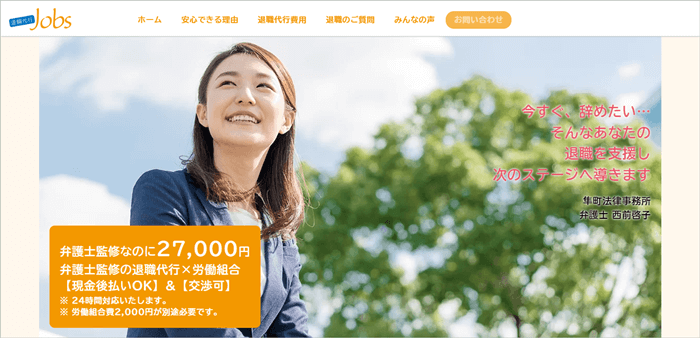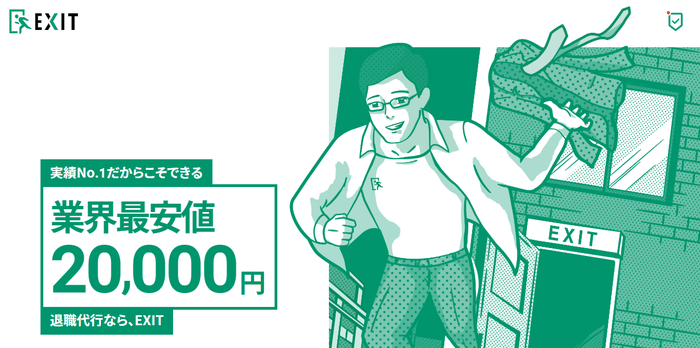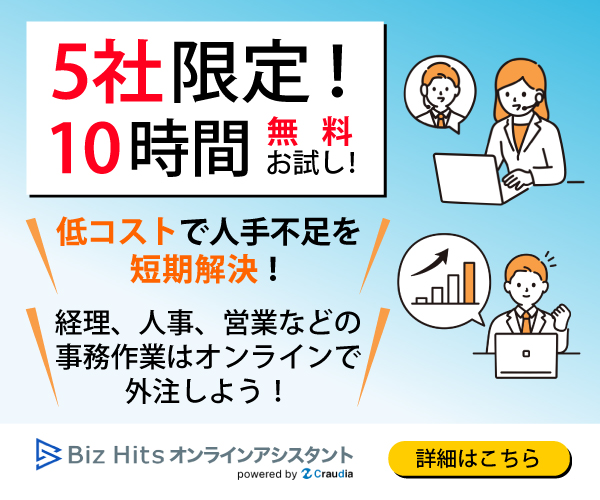- 退職したいけれど上司に言い出せない。
- 会社に行くのも苦痛。出社せずに退職してしまいたい。
上記のような悩みを抱えている方に人気なのが「退職代行サービス」です。
退職代行サービスを使えば、会社・上司と直接連絡をとらずに退職できます。
しかし退職代行サービスを使ったことがない方だと、「退職代行サービスって怪しそう」「どのサービスなら安心なのかわからない」と不安をもつことでしょう。
結論から言いますと、以下の退職代行サービスなら安心して利用できます。
- 退職代行ガーディアン
- 退職代行Jobs
- 辞めるんです
- フォーゲル綜合法律事務所
- 弁護士法人みやび
- 退職代行EXIT
上記の退職代行サービスはいずれも弁護士や労働組合が関わっているサービスだからです。
この記事では、「おすすめの退職代行サービス」「退職代行を使うメリットや注意点・リスク」について解説します。
退職代行サービスおすすめ6選!サービス概要も紹介
おすすめの退職代行サービスは以下の6つです。
- 退職代行ガーディアン
- 退職代行Jobs
- 辞めるんです
- フォーゲル綜合法律事務所
- 弁護士法人みやび
- 退職代行EXIT
それぞれの退職代行サービスの特徴を紹介します。
退職代行ガーディアンは会社と交渉したい場合におすすめ
退職代行ガーディアンは、東京労働経済組合という労働組合が運営している退職代行サービスです。
退職代行ガーディアンは、退職にあたり会社と交渉したい場合におすすめ。
労働組合なら「未払い給与・残業代の請求」などの交渉もできるからですね。
退職代行ガーディアンなら、未払い給与や残業代の請求に成功した場合に追加料金がかからないのもメリットです。
「会社と交渉したいが、できるだけ費用は安くしたい」という方におすすめできます。
| タイプ | 労働組合が運営 |
|---|---|
| 料金 | 24,800円(※) |
| LINE対応の有無 | あり |
| 対応エリア | 全国 |
| 返金保証 | なし |
※退職代行が終わっても相談はずーっと無料(2025年3月時点)
退職代行Jobsは労働組合と連携していて安心
退職代行Jobsは労働組合と連携しており、安心して利用できる退職代行サービスです。
追加料金2,000円を払って労働組合に加入すれば、退職にあたり会社(職場)との交渉が必要な場合にも対応できるからですね。
料金が比較的リーズナブルで、相談から会社への連絡までが早いのも魅力です。
「安心して利用したい」「すぐ辞めたい」という方におすすめできます。
| タイプ | 民間企業が運営(弁護士監修&労働組合と連携) |
|---|---|
| 料金(税込) | 27,000円(※) |
| LINE対応の有無 | あり |
| 対応エリア | 全国 |
| 返金保証 | あり |
(※)労働組合費2,000円が別途必要です。(2025年3月時点)
「辞めるんです」は早く辞めたい人におすすめ
「辞めるんです」はとにかく早く会社を辞めたい人におすすめしたい退職代行サービスです。
「辞めるんです」のLINEは24時間受付可能で返信も早く、即日で会社に退職連絡してくれるからですね。
これまで7,000件以上の実績があり、すべての利用者が退職を実現しているのも、安心して利用できるポイント。
民間企業運営のサービスで退職意向の伝言しかできませんので、「未払い給与など会社との交渉事はなく、とにかくすぐ退職したい」という人におすすめです。
| タイプ | 民間企業が運営(弁護士監修) |
|---|---|
| 料金(税込) | 27,000円 |
| LINE対応の有無 | あり |
| 対応エリア | 全国 |
| 返金保証 | あり |
フォーゲル綜合法律事務所は弁護士対応だがリーズナブル
フォーゲル綜合法律事務所は弁護士事務所が運営している退職代行サービス。
「弁護士が対応する退職代行サービスは料金設定が高め」と言われますが、フォーゲル綜合法律事務所はリーズナブルな料金設定が魅力です。
弁護士事務所が運営する退職代行サービスによくある「追加料金」「成功報酬」がないため、ベーシックなプランなら33,000円で利用できます。
また「対応が早い」「会社への連絡の丁寧さ」の点でも定評があり、全体的に安心して利用できる退職代行サービスだと言えるでしょう。
「弁護士対応の退職代行サービスが希望だけれど、料金が不安」という方におすすめです。
| タイプ | 弁護士事務所が運営 |
|---|---|
| 料金(税込) | 25,000円~110,000円 |
| LINE対応の有無 | あり |
| 対応エリア | 全国 |
| 返金保証 | あり |
弁護士法人みやびなら難しいケースも任せられる
弁護士法人みやびなら、民間企業の退職代行サービスからは断られるような難しい退職でも対応可能です。
弁護士事務所が運営しており、法的な問題にも対処できる退職代行サービスだからですね。
そのため「会社に借金しており、退職したいと言ったら揉めそう」「トラブルなく円満に退職したい」という方におすすめ。
ただし比較的料金が高く、ケースによって追加料金が発生するのはデメリットです。
| タイプ | 弁護士事務所が運営 |
|---|---|
| 料金 | 27,500円~77,000円(※) |
| LINE対応の有無 | あり |
| 対応エリア | 全国 |
| 返金保証 | なし |
(※)ケースにより追加料金あり(残業代・退職金などの20%)
退職代行EXITは費用を安く抑えたい方におすすめ
退職代行EXITは、退職代行サービスにかかる費用を安く抑えたい方におすすめです。
退職代行EXITは、なんと追加料金なしの20,000円(2回目以降の利用なら10,000円)で利用できるからですね。
安くても会社連絡時の対応などは丁寧で、ちゃんと退職できます。
民間企業のため「退職意向の伝言」しかできないので、「給与の未払いなど、会社との交渉事がない」というケースのみ使えます。
「とにかく料金を安くしたい」という方におすすめです。
| タイプ | 民間企業が運営(弁護士監修) |
|---|---|
| 料金(税込) | 20,000円(リピーター:15,000円) |
| LINE対応の有無 | あり |
| 対応エリア | 全国 |
| 返金保証 | あり |
退職代行サービスとは?内容や種類を解説
退職代行とは、退職を希望する人に変わって代行業者や弁護士が代わりに退職の意志を伝えたり、退職関連の交渉などを行ってくれたりするサービスです。
2000年代後半頃にサービスが登場して以降、現在では知名度も浸透し、利用者も代行業者も増加傾向にあります。
長時間労働やハラスメントなどがあるにも関わらず、「なかなか言い出せない」「辞められない」という状況を打破する目的のもと誕生したサービスです。
人手不足の深刻化による引き止めや、働き方に対する価値観の変化などで、今後も退職代行サービスの需要は高まるだろうと予測されています。
退職代行サービスの種類①「民間サービス」なら手軽に利用できる
民間企業が運営する退職代行サービスは、手軽さが魅力です。
弁護士事務所や労働組合が運営するサービスと比べ、安価で利用できるところが多いからですね。
ただ民間サービスだと「利用者に代わり、退職の意向を伝えること」しかできません。
民間企業が「未払い給与の請求をする」など、会社との協議・交渉や法的な問題に携わってしまうと違法となります。
料金相場は2万円~3万円です。
| 民間の退職代行サービス | 料金(税込) |
|---|---|
| 退職代行Jobs | 27,000円(※) |
| 辞めるんです | 27,000円 |
| 退職代行EXIT | 20,000円 |
| モームリ | 22,000円(正社員) |
| スタイリード | 20,000円(正社員) |
(調査日:2025年3月20日)
(※)労働組合費2,000円が別途必要です。(2025年3月時点)
退職代行サービスの種類②「弁護士事務所」は法的な問題も対処してくれる
弁護士事務所が運営する退職代行サービスなら、法的な問題にも対処できます。
弁護士に退職代行をしてもらえるからですね。
例えば以下のようなケースに対応可能です。
- 未払い給与や残業代の申請
- 退職金の請求
- ハラスメント行為についての慰謝料請求
「法律の専門家が対応してくれる」「法律上のトラブルが起こりにくい」という安心感もあります。
ただし弁護士対応の場合、民間企業や労働組合が運営する退職代行サービスよりお金がかかります。
また「未払い給与の請求」「退職金の請求」については、別途「成功報酬」が請求されるケースも。
お金の面でも安心して利用するために、事前に料金体系を調べておきましょう。
料金相場は、2万円台~10万円前後です。
金銭の絡む請求があるケースでは、上記相場にプラスして、成功報酬や追加料金が別途必要となります。
| 弁護士事務所運営の退職代行サービス | 料金(税込) |
|---|---|
| フォーゲル綜合法律事務所 | 25,000円~110,000円 |
| 弁護士法人みやび | 27,500円~77,000円 |
| 退職110番 | 43,800円 |
(調査日:2025年3月20日)
退職代行サービスの種類③「労働組合・ユニオン」なら会社との交渉の場を持てる
労働組合・ユニオンが運営する退職代行サービスなら、確実に会社と交渉可能です。
労働組合は「団体交渉権」を持っており、会社側は労働組合からの交渉を無視できないからですね。
そのため「未払い給与・残業代の支払い」といった交渉もできます。
ただし労働組合は法律の専門家ではないため、「慰謝料や損害賠償の請求」「法律的な相談」はできません。
料金相場は2万円~2万5,000円です。
| 労働組合・ユニオン運営の退職代行サービス | 料金(税込) |
|---|---|
| 退職代行トリケシ | 25,000円 |
| リーガルジャパン | 25,000円(※) |
| 退職代行退職サポート | 20,000円 |
(調査日:2025年3月20日)
(※)別途、労働組合加入費2,000円が必要
退職代行サービスを選ぶ際のコツ
サービスの基本や種類が理解できたら、さらに選択肢を絞り込むための選ぶ際のコツを紹介します。
- どこまでサポートしてもらうのか状況に合ったサービスを選ぶ
- 民間運営なら労働組合や弁護士と連携しているサービスを選ぶ
- 無理なく支払える料金設定か事前確認する
- サポート・レスポンスの速さをチェックする
- 企業側からの評価が高いかを調べる
- 退職できるか不安なら返金保証があるサービスを選ぶ
順に解説するので参考にしてみてください。
どこまでサポートしてもらうのか状況に合ったサービスを選ぶ
まずは、どこまでサポートしてもらうのか状況に合ったサービスを選びましょう。
退職代行サービスは種類によって、サポート範囲が異なります。
以下の表にサポート内容と、対応している退職代行サービスをまとめてみました。
| サポート内容 | 対応している退職代行サービス |
|---|---|
| 会社への退職意思の連絡代行 | 民間/労働組合/弁護士 |
| 会社との交渉(有給消化、退職日など) | 労働組合/弁護士 |
| 書類請求(離職票、源泉徴収票など) | 労働組合/弁護士 |
| 未払い給与・退職金などの請求 | 弁護士 |
| 法律業務(賠償請求、裁判対応など) | 弁護士 |
勤務先がきちんと退職手続きに対応してくれる会社で、未払い給与の問題などを抱えていなければ、退職意思の連絡代行のみサポートの民間サービスを選択するのもありです。
しかし、過去に他の社員との間で退職トラブルがあったり、セクハラやパワハラなどを受けていたりするなら、サポート範囲の広い「労働組合」か「弁護士事務所」が運営する代行サービスをおすすめします。
民間運営なら労働組合や弁護士と連携しているサービスを選ぶ
民間企業が運営する退職代行を選択肢に入れる際は、労働組合や弁護士と連携しているサービスを選びましょう。
退職の意思を伝えるだけなら民間業者単独でも対応可能ですが、会社との交渉が必要となった場合、民間業者だけでは対応できません。
はじめは「退職意思を伝えてもらうだけで大丈夫」と思っていても、離職票が届かない、給料が支払われないなど、交渉が必要になる可能性もあります。
万が一のときのために、民間サービスを選ぶ際は、前もって連携の有無を確認しておきましょう。
連携しているサービスは公式サイト上に、「労働組合と連携」などの記載があります。
注意したいのが「弁護士監修」という記載です。
監修のみで、実際は弁護士が法的なサポートを提供していない場合もあるので確認してみてください。
また、提携している労働組合が正式に認められている団体かも確認しておくことをおすすめします。
無理なく支払える料金設定か事前確認する
無理なく支払える料金設定か、事前に確認することも大切です。
退職代行サービスの種類によっても料金相場が異なりますし、オプションなどが発生することもあるからです。
例えば、基本料金は安くても、「残業代請求」の代行を依頼すると、オプションで別途費用を請求されることがあります。
とくに弁護士事務所が運営する退職代行サービスは、「回収額の20%の報酬が発生します」など設けられていることも多いです。
また、労働組合運営の退職代行サービスでは、労働組合への加入費を別途求められることも。
さらに注意したいのが、雇用形態によって料金設定しているサービスもあることです。
パート・アルバイトの料金が安く設定される傾向にあるので、正社員で退職を希望する人は注意が必要です。
サポート・レスポンスの速さをチェックする
退職代行サービス選びでは、対応・レスポンスが速いことも重要です。
退職代行サービスを利用したい人の中には「すぐ辞めたい」「もう明日から仕事に行きたくない」と思い詰めている人も多いからですね。
「辞めたいときにすぐ連絡が取れ、動いてくれる」のは、退職代行サービスを利用する人にとって大きなメリットです。
退職代行サービスの中には「LINEで相談して1分以内に返信がある」など、かなりレスポンスが早いところもあります。
また、「即日対応」「24時間連絡可」のサービスを押さえておくのもおすすめ。
退職意向の連絡をしてもらったその日から、出社しなくても済みますし、24時間対応なら夜中に辞めたいと決心した場合でもすぐ連絡が取れます。
企業側からの評価が高いかを調べる
企業側からの評価の高さも選ぶ際に調べておきましょう。
対応の良い退職代行サービスなら、会社ともトラブルを起こさず、穏便かつ円満に退職できるからですね。
例えば、会社の言い分を一切聞かず一方的に話を続けたり、高圧的な伝え方だったりする場合、企業側も反発して退職手続きがスムーズに進まなくなることも。
また、評判が高い退職代行サービスであれば、「会社から直接自分のところへ連絡しないでほしい」といった希望もきちんと伝えてくれるため、トラブルにもなりにくいと考えられます。
どのような事情があっても、スムーズに退職できるのが理想的です。
退職できるか不安なら返金保証があるサービスを選ぶ
本当に退職できるか不安なら、返金保証がある退職代行サービスを選ぶといいでしょう。
基本的に退職代行の成功率は高いと言われていますが、100%成功できるとは言い切れないからです。
サービスの選択を誤ったり、特殊なケースだったりする場合、失敗する可能性もあります。
「退職率100%」を謳っているサービスもありますが、成功率だけでなく、相談実績の多さも重要ポイントです。
例えば、相談件数10件と1万件とでは、同じ成功率100%でも、蓄積されたノウハウや対応力に違いがあります。
「初めての利用で不安」「自分のケースは難しいかもしれない」という人は、返金保証の有無をチェックしてみてください。
退職代行サービスを利用するメリット
退職代行を利用すると、以下のようなメリットがあります。
- 自分で上司に退職を切り出さなくて済む
- 会社の人事や関係者とのやり取りも必要なくなる
- 誰とも顔を合わさず辞められる
- 即日退職できる可能性がある
- 有給休暇を消化して退職できる
詳しく解説していくので、順番にチェックしてみてください。
自分で上司に退職を切り出さなくて済む
自分で上司に退職を切り出さなくて済むのは、退職代行の大きなメリットです。
退職代行サービスという「第三者」から、退職について伝えてもらえるからですね。
辞める本人から直接上司に話をするわけではないので、心理的負担がかなり軽減され、慰留や叱責を直接受ける心配もありません。
自分から言い出せない人には心強いサービスだと言えます。
とくに上司と良好な関係を築けていない場合や、退職の意思を伝えるのが難しいと感じている人は、退職代行サービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
会社の人事や関係者とのやり取りも必要なくなる
退職代行を利用すれば、会社の人事や関係者ともやり取りする必要がありません。
退職代行サービスが、直接連絡を取らないようにと伝えてくれるからです。
上司や会社へ退職意向を伝えてもらったら、退職が完了するわけではありません。
「退職手続き」「業務の引き継ぎ」「会社への返却物」などが発生するため、人事や関係者と連絡を取る必要が出てきます。
しかし、「連絡を取りたくない」という意向を伝えておけば、やり取りや調整もすべて代行してもらえます。
また、上司以外からの引き留めや、退職の意思確認の連絡が入ることも防げるでしょう。
退職するのに会社の人間と連絡を取り合うことに抵抗がある人は、退職代行サービスに連絡関連の対応を依頼してみてください。
誰とも顔を合わさず辞められる
誰とも顔を合わさずに辞められるのも、退職代行サービスを利用するメリットです。
会社へ行かなくても済むように、段取りをしてくれるからですね。
事前に打ち合わせやヒアリングシートなどで、私物や返却物の有無を確認し、取り扱いについて決めておきます。
例えば、職場に置いてある私物のマグカップや、社員証などの返却物です。
基本的に郵送で済むよう対応してもらえるので、会社に行く必要はありません。
また、退職に必要な「源泉徴収票」「離職票」「社会保険資格喪失証明書」などの書類も、会社と連絡を取り合って、返却や受け取りについて調整してくれます。
退職届などのテンプレートを用意してくれているサービスもあるので、手続きがスムーズに進むでしょう。
退職の際、職場の人と顔を合わせたくない人は多いものです。
「手続きのために会社へ来て欲しい」「話し合いをしよう」「私物を取りに来るように」などの要求に対する不安を感じずに済むのは、大きなメリットと言えるでしょう。
即日退職できる可能性がある
民法第627条では、雇用期間の定めがない場合には、いつでも解約の申し入れができ、2週間を経過すれば退職できると定められています。
そのため、「すぐ辞めたくても、即日退職は難しいのでは」と思っている人もいるでしょう。
退職代行サービスを利用すれば、即日退職できる可能性があります。
依頼する日時にもよりますが、依頼から数時間後には、退職代行サービスが職場に退職連絡を入れ、手続きや調整を行ってくれるからですね。
ただし、雇用期間の定めがある「契約社員」や「派遣社員」は契約内容に基づいて手続きが進むため、即日の退職が難しい場合もあります。
退職時期について退職代行サービスに確認することをおすすめします。
「自分では即日退職の意思を伝えづらい」「すぐ辞められないとずるずる引き延ばされそう」などであれば、退職代行にお願いしてみてはいかがでしょうか。
有給休暇を消化して退職できる
退職代行サービスを利用すれば、有給休暇を消化して退職することも可能です。
退職時にあやふやになりがちな有給取得についても、会社に「取得してから辞めたい」旨を伝えてくれるので消化できます。
有給休暇は労働基準法第39条で定められた労働者の権利で、申請すれば原則として取得可能です。
企業側が拒否すれば法律違反となるのですが、制度を理解していないと、取得できるのに諦めてしまうケースもあります。
例えば、10日間の有給休暇が残っていれば、書類上の退職日は10日後でも、その日まで会社に行く必要はありません。
「有給を使いきってから退職したい」「有給休暇のことを会社に言いづらい」なら、ぜひ退職代行サービスを使って、有給休暇をすべて消化できるよう対応してもらいましょう。
退職代行サービスのリスクと注意点
退職代行サービスのリスクは次のとおりです。
- 費用負担が大きくもったいなく感じることもある
- 悪質な代行業者に依頼するとトラブルに巻き込まれる可能性がある
- 会社に迷惑をかける可能性がある
注意点とあわせて解説していくので、リスクを避けるための参考にしてみてください。
費用負担が大きくもったいなく感じることもある
退職代行サービスを利用する人の中には、費用負担が大きく、もったいなく感じることもあるでしょう。
サービスの種類にもよりますが相場は2万円代~となっており、「収入が少ない」「貯金がない」「次の仕事が決まっていない」場合などは、出費が痛手になることも。
サポート内容や利用するサービスのタイプによっては料金が高額になったり、オプションの追加が必要になって、さらに負担が大きくなったりすることも考えられます。
もちろん、利用者の中には「言い出せない退職意向を数万円で伝えてもらえるのなら安い」「有給休暇も消化しきれるし、未払いの給料や退職金も払ってもらえたから、お金を払った価値があった」という人も。
自分で退職を伝えて手続きすれば費用はかかりません。
悪質な業者に依頼するとトラブルに巻き込まれる可能性がある
悪質な業者に依頼すると、トラブルに巻き込まれる可能性もあります。
「弁護士資格がないのに会社側と協議・交渉をしてしまう」「態度が悪く会社側とトラブルを起こす」といった退職代行サービスもあるからですね。
違法行為をした場合に罰されるのは利用者ではなく退職代行サービスですが、利用者も事情を聞かれるなど、トラブルに巻き込まれる可能性はあります。
また悪質な業者の場合、「料金を払ったあと、業者と連絡がとれなくなった」「退職関係書類を送付してくれない」などのトラブルも考えられます。
会社に迷惑をかける可能性がある
退職代行サービスを利用すると、会社に迷惑をかける可能性があります。
「すぐ辞めたい」「会社側と対話をしたくない」という状況で利用する人が多いため、会社側は急な退職に対応できず、困ってしまうわけです。
とくに後任が決まっていない状態での退職は、引き継ぎが行われないので、穴埋めをする他の社員の負担が大きくなることにもなりかねません。
また、「なぜ話してくれなかったのか」とショックを受けたり、「なぜ代行サービスを使ってまで急に辞めたのだろう」と心配したりする上司や同僚もいます。
ハラスメントや事前に聞いていた内容の条件と違ったなど、会社側に非のあるケースもありますが、話し合いで解決を図れる可能性があることも理解しておいてください。
退職代行サービスの上手な活用法
退職代行サービスを上手に活用するためのコツやポイントを紹介します。
- 利用申し込み前に退職準備をしておく
- 退職に関する希望や退職代行サービスへの要望は事前にまとめておく
- 無職期間を短くしたいなら先に転職先を決めてから退職代行を利用する
- 退職代行との契約内容は必ず確認する
詳しく解説するので、利用を検討している人は参考にしてみてください。
サービス利用の申し込み前に退職準備をしておく
退職代行サービスに利用の申し込みをする前に、退職準備を進めておきましょう。
退職代行ではできないこともあるからです。
具体的には、以下のような準備をしておくと、会社との調整が少なく済み、退職がよりスムーズに進みます。
- 職場で使っている私物をもって帰る
- 引き継ぎ書を作成しておく
私物に関しては会社で処分してもらうことも可能ですが、引き継ぎ内容に関しては、何の準備もないと迷惑をかけてしまいますし、確認の連絡が入ることにもなってしまいます。
とくに「あなたしか知らないこと」がある場合、引き継ぎを怠ると業務に影響を与え、損害が出てしまうことも考えられるため要注意です。
また社宅に住んでいる場合は、退職後いつまでに社宅を出ないといけないか就業規則で確認し、引っ越し先の手配もしておきましょう。
退職に関する希望や退職代行サービスへの要望は事前にまとめておく
退職に関する希望や退職代行サービスへの要望は、事前にまとめておくのがおすすめ。
申し込み後、「LINE」「メール」「電話」「対面」などで打ち合わせを行いますが、伝え忘れや伝え間違いがあると、希望通りのかたちで退職できない可能性があるからです。
主にまとめておきたいのは次の点です。
- 希望退職日
- 有給休暇の利用
- 貸与物の有無や返却方法
- 会社から連絡がきた場合の対応
- 未払い給与や退職金の扱いついて
- 退職証明書など必要書類
- 引き継ぎのデータや書面の有無
例えば「有給休暇が残っているのに退職代行サービスに伝えていなかったせいで、有給消化ができなかった」といったことも考えられます。
すでに転職先が決まっている場合には、希望退職日も「できるだけ早く」といった指示ではなく、「入社日に間に合うよう、〇月〇日までに」と正確に伝えるのがおすすめです。
無職期間を短くしたいなら先に転職先を決めてから退職代行を利用する
無職期間を短くしたい場合には、先に転職先を決めてから退職代行サービスを利用しましょう。
退職代行は短期間でスムーズに退職できるため、転職先が決まっていないと無職期間が発生していまいます。
無職期間が長引くと、妥協して次の会社を選んでしまい、またすぐ「辞めたい」と退職代行サービスを使うことにも。
ブランクをつくりたくない人は、先に転職活動を行い、内定獲得後に退職代行サービスを利用するのが効率的です。
もちろん、切羽詰まっている状況だと転職先が決まるまで仕事を続けられない人もいるでしょう。
そのような人には、「トリケシ」や「リーガルジャパン」などの、転職支援つきの退職代行サービスの活用がおすすめ。
なぜ退職に至ったかなどの状況を理解してもらった上でサポートを受けられるため、心強いのではないでしょうか。
なお無職期間ができる場合は、失業保険の申請手続きを忘れないようにしましょう。
退職代行との契約内容は必ず確認する
退職代行サービスを利用する際は、契約内容をしっかり確認しておくことが大切です。
思い違いがあると「こんなはずではなかった」と後悔することにもなりかねません。
例えば、基本料金にすべて含まれていると思っていたら、交渉や書類作成が有料だったというケースもあります。
また、Webサイトの記載と、実際の料金やサポート範囲が違うこともあるため、見積書や契約書の内容は必ずチェックするようにしましょう。
とくに要チェックなのが以下の点です。
- 基本サービスに含まれている内容
- 退職日の変更ができるか
- 退職後のサポートの有無や期間
- キャンセル料は発生するか
思うように退職できず、別のサービスを頼ることになれば、金銭的にも精神的にも余計な負担がかかってしまいます。
不明点があれば事前に問い合わせ、納得した上でサービスを利用するようにしましょう。
退職代行を利用する際の一連の流れ
退職代行サービスは、以下のような流れで利用するのが一般的です。
- 退職代行サービスに相談する
- 退職代行サービスに料金を支払う
- 退職代行サービスから職場へ、退職について連絡
- 退職手続き
一連の流れを理解することで、退職代行サービスをより効率的に利用していきましょう。
1.退職代行サービスに現在の自分の状況や退職の悩みを相談する
まずは退職代行サービスに、現在の自分の状況や退職についての悩みを相談します。
「信頼できそうなサービスかどうか」「利用すべきかどうか」を判断するためです。
もちろん利用前に疑問点について質問もできます。
「申し込み後の流れ」「職場・上司から直接自分に連絡が入ることはないのか」など、不安なことは聞いておきましょう。
退職代行サービスへの連絡方法としては「電話」「LINE」などがあり、最近ではLINEでやりとりするサービスが多いようです。
「LINEで大丈夫?」と思う方もいるかもしれませんが、LINEには「相談しやすい」「相談内容が文字になって残る」というメリットがあります。
相談は基本的に無料なので、退職代行サービスが気になっているなら、まずは相談してみましょう。
ただし相談相手が弁護士の場合、相談料が必要になることもあります。
念のため、相談料の有無について事前にチェックしておきましょう。
2.サービス内容に納得できたら料金を支払う
サービス内容や料金に納得できたら、料金を支払います。
申し込みを確定させ、退職代行業務を始めてもらうためですね。
「料金は後払い」の退職代行サービスもありますが、前払い制が一般的です。
支払い方法はサービスにより異なりますが、「クレジットカード決済」「口座振り込み」などから選べるようになっています。
退職代行サービスの利用を考えた時点でお金を用意しておくと、スムーズに支払いできます。
3.退職代行サービスが企業に連絡してあなたの代わりに退職の意志を伝える
料金支払い後、退職代行サービスからあなたの勤務先へ連絡が入ります。
あなたの代わりに退職の意思を職場に伝えるためですね。
料金支払いから数時間後には連絡を入れてくれる退職代行サービスが多く、対応はスピーディー。
利用者側がすることはないので、退職代行サービスに任せて待ちましょう。
4.退職手続きを行う
退職意思を伝えてもらったら、退職手続きへと進みます。
基本的な手続きの流れもサポートしてもらえるので、スムーズに退職日を迎えられるでしょう。
主に必要となる手続きは以下のとおりです。
- 退職届の提出(郵送)
- 会社から貸与されていた制服などの返却
- 社員証や健康保険証の返却
退職届についてはテンプレートを提供してくれたり、作成代行してくれたりする退職代行サービスもあります。
「返却物の内容」「返却期限」は、退職代行サービスから連絡があるので、期限を守って対応しましょう。

退職代行サービスの中には、退職後のアフターサービスを提供しているケースも。
例えば、弁護士事務所運営のサービスでは、未払い賃金の交渉をしてくれる場合もあります。
また、有料職業紹介許可番号を取得している運営元では、転職先を紹介してもらうことも可能です。
しかし、運営元の実態をしっかり確認しないと、思わぬトラブルに巻き込まれることもあるので、慎重に選ぶことが大切です。
アフターフォローを希望するなら、信頼できるサービスを選び、不審な代行サービスには引っかからないように注意しましょう。
退職代行サービス利用に関するよくある質問
退職代行サービス利用に関してよく寄せられる質問を紹介します。
順番にお答えするので、気になる質問があればチェックしてみてください。
Q.退職代行を使うと「ヤバい人」「変な人」と思われそうで不安です。
A.結論から言いますと、退職代行を使うのは「ヤバいこと」でも「変なこと」でもありません。
「退職代行サービスを使って退職した同僚への印象」について聞いた調査では、「非常識」などと否定的な回答をした人は少なくなっています。
また、マイナビキャリアリサーチLabの調査によると、「直近1年間(2023年6月以降)に転職した人の退職代行サービス利用率」は16.6%と、浸透してきていることがわかります。
「上司が高圧的」などの理由でなかなか退職を言い出せない場合には、退職代行サービスの利用を検討してみましょう。
Q.退職代行サービスはどんな職業でも使えますか?
A.基本的にはどんな職業でも退職代行サービスは使えます。
雇用契約に基づく就労ならば、退職についての基本的な考え方は同じだからです。
一般企業で働いているなら、職種に関わらず退職代行サービスは利用できると考えてOK。
アルバイト・パートの退職代行を請け負っている退職代行サービスもあります。
ただし民間の退職代行サービスですと、公務員は対象外にしていることもあります。
国・自治体が退職代行サービスからの連絡に対応できない可能性があるからです。
公務員の退職代行なら、弁護士事務所運営のサービスを利用しましょう。
Q.退職代行を使うと転職活動に悪影響が出るのでは?
A.結論から言いますと、退職代行の利用が転職活動に影響することはほぼありません。
「退職代行を利用した」と転職先に知られることは、ほとんどないからです。
また退職代行サービスの利用を知られたとしても、必ずしもネガティブな印象になるとは限りません。
最近では退職代行サービスの利用に理解を示す人も多いからです。
「どうしても退職代行サービスの利用を知られたくない」という場合は、「SNSに退職代行利用について投稿しない」「うっかり口を滑らせないように注意する」と心掛けましょう。
Q.すでに自分から退職を申し出ていますがサービスは利用できますか?
A.退職の意向を会社に伝えている人の利用も可能です。
「会社からの引き留めに困っている」「残りの有給休暇や退職金に関する話が進まない」などの理由で、退職代行サービスを利用する人もいます。
やり取りを引き継いで、スムーズに退職できるようサポートしてもらえるので、ぜひ相談してみてください。
退職を伝えた後のサポートとなるので、交渉の可能な労働組合または弁護士事務所が運営するサービスを利用しましょう。
Q.退職代行を使う場合、会社とのLINEやメールはブロックしても問題ないですか?
結論から言いますと、どのサービスを利用するかによってブロックの可否が変わってきます。
労働組合や弁護士事務所が運営する退職代行サービスなら、代理人がやり取りや交渉を代行してくれるため、基本的にブロックしても問題ありません。
しかし、民間企業が運営するサービスは、会社との交渉はできず、あくまでも退職意向を伝えるサポートにとどまります。
そのため、会社との連絡を完全に遮断してしまうと、次のようなリスクが生じます。
- 退職手続きに必要なやり取りができなくなる。
- あなたしかわからない業務の確認・引き継ぎができず、トラブルや損害につながる可能性がある。
民間企業運営のサービスを利用する場合は、一定期間は会社からの連絡が受けられるようにしておくほうがいいでしょう。
【まとめ】退職代行サービスがおすすめの方
退職代行サービスの利用がおすすめ方をまとめますと次のとおりです。
- 自分では退職の意向を伝えられない
- 退職の意向を伝えたが、とりあってもらえなかった
- 会社に行かず、すぐにでも退職したい
退職代行サービスを利用すればスムーズに退職でき、有給が十分残っていれば「明日から出社しなくていい」といったことも可能です。
退職代行サービスには3つの種類があり、もっとも対応範囲が広いのは「弁護士が対応する退職代行サービス」となっています。
しかし弁護士が対応するサービスは料金がやや高めなので、「退職を伝えてくれるだけでいい」なら民間サービスでもOK。
民間サービスを利用する場合には、法的なトラブルに巻き込まれないよう、弁護士や労働組合と連携しているサービスを選びましょう。
多くの退職代行サービスはLINEから利用について相談でき、スピーディーな対応が可能となっています。
この記事が「次に進みたい」と考えつつも一歩踏み出せない方の助けになれば幸いです。